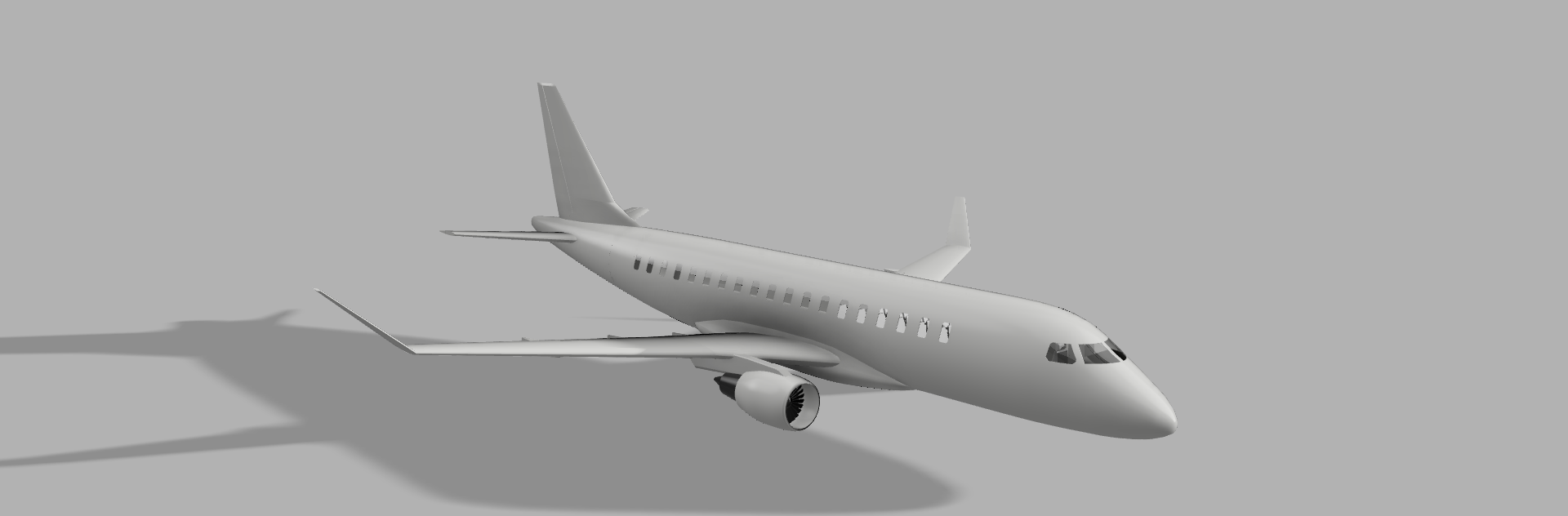ゼミってどんなことするの?
航空学群のゼミってどんなことが学べるの?先生や先輩の話を聞きに行ったら、想像以上にプロフェッショナルだった!
RELEASED 2025.3.19
航空学群は、業界出身の教授陣による専門性の高いゼミも魅力!
ゼミは、自分が関心のあるテーマを選び、研究や発表、ディスカッションや課外活動を行う「演習型」の学びが特徴。先生の解説が中心の「講義」とは一味違って、大学生ならではの能動的な学習スタイルです。
桜美林大学の航空学群では、3年生の春学期からゼミを履修することが可能。航空業界で活躍してきた先生方の研究を間近で感じられるのは、ゼミならではの魅力です。所属するコースに関係なく選択できるのもポイント!
今回は、そんな多種多様な航空学群のゼミを知ってもらうべく、2つのゼミの先生と先輩たちにお話を聞きに行ってきました!